|
「日本文化のカタリとハナシ―日本の民俗文化におけるハナシ・カタリ・ヨミ・トナエ等の口承文芸の伝統と話芸について」
● 2014年2月15日(土)午後2時-4時30分
● 目黒青少年プラザ視聴覚室
● 話題提供:飯倉義之先生(國學院大學)

講演要旨
民話を分類すると-昔話・伝説・世間話
今日は、日本の伝統的な口伝えの物語、昔話や伝説などでは、どういうことばの使い方がされているのかということについてお話します。
世の中には民話とか説話、おとぎ話、童話などさまざまな名前のものがあって、なんとなく囲炉裏端で話されるお話、のようなぼんやりとしたイメージがあり、一般ではそれも間違いではありません。しかし民俗学ではそれぞれを区別しています。まず、それを紹介しておきましょう。
民俗学では、韻を踏まずに、また、歌でもなく、一種の筋書きに沿って伝えられるお話を民間説話と読んでいます。それを略して民話ということもあります。英語のFalk Talesの略語なのでどちらで呼んでもいいのですね。その民話をさらに、昔話・伝説・世間話と三つに分類して考えています。

当日の配布資料
※クリックすると拡大した画像が見られます(別ウィンドウが開きます)。
神話に対する民話
その民話は、神話に対することばと考えてもらっていいと思います。民話と神話とどこが違うかというと、内容面に依拠していて、民話は民の話、出てくるものたちはこの世にいる人間や動物、鬼や天狗も出てきますが、この世界にいるものたちが、この世界でどうふるまうのか、ということに注目している話です。一方神話は、この世界の成り立ちそのものを語るもの、神様がこの世界をどう創って、この世界のルールをどう決めて行ったのか、それを語る説話です。日本の神話ではイザナギ・イザナミが日本列島をどうやって作っていったのか、から始まりますしキリスト教の神話、旧約聖書ですね、唯一神が光あれといって昼と夜を分けた、そのように昼と夜や、人間はどうやって火を手に入れたか、人間はなぜ死ぬのか、のような根源的なことの始まりを語っていくのが神話です。
なぞなぞやことわざ
民俗学では、神話や民話をさらに大きく、口承文芸というくくりでくくって考えています。この口承文芸を昔話・伝説・世間話と分けて考えようと提唱したのが、日本民俗学の祖といわれている柳田國男です。口承文芸というとすぐに民話と思われがちですが、もっと広い分野を含んでいます。例えば謎々。「目がひとつ、足がひとつ、飛んだあとにしるしを残すものなぁに=答え:針。ことばの使い方の技術が遊戯化したものが謎々です。○○はなぁに、と答えを求めるものを二段謎といいます。これがもう少し精度があがったものが三段謎、「急ぐ人とかけて、曲がった松と解きます、その心は、どちらもはしらにゃなりません」というような謎々ですね。これは謎を解かせるというより、ここまでよく考えたでしょう?ということの楽しさになります。
それから、ことわざ。ことばのわざ、といっているように、人生の経験的な真理をたとえにしてあらわしたものです。「急がば回れ」など、人生で急いであせってすると却ってうまくいかないことがある、という経験的な真理を簡潔な、整ったことばであらわしています。柳田國男はかつて、ことわざは議論の重要な技術だったろうと言っています。たとえ話で説得されると、その説得が図星であればあるほど、反論できなくなるものです。
名づけの技術
ことばの技術を突き詰めていくと、新語や命名などにつながっていきます。新しい物事につける名前、どちらも名づけの技術です。今の生活ではわかりづらいかもしれませんが、たとえば明治時代、外国から新しい文物がたくさん入ってきて、それに日本語あるいは土地々々のことばで名前を付ける、その時に新語・命名の技術が活用されました。例えば明治時代に日本全国に鉄道が広がっていく、土を盛ってバラストを敷いて、枕木を置いてレールを敷く。今まで全く違う地形になる。鉄道の資材にくっついてきた種が芽生えて今までにない植生が生まれる。今私たちはコスモスとかセイタカアワダチソウと読んでいますが、それらは鉄道が敷かれた後に全国できれいな花を咲かせたので、鉄道草と呼ばれました。また、トマトは幕末に観賞用として日本に入ってきましたが、緑だった実が、ナスだと紫になるところが、これは赤くなる、そこからキチガイナスビと呼んだ地方が結構ありました。このように土地々々でぴったりと思われる名前をつける、方言に残っていますが、たとえば北関東の「いじやける」胸がむかむかすることですが、生活の中でぴったりくることばを創って自分たちの感じ方を表現するのです。こういう技術が口承文芸の根源のところにある、と柳田國男は説きました。
最近の大学生のことばを聞いていますと、たとえば「アカセン前に集合」とか言っていました。アカデミックセンターを略してアカセンなんですね、昔のことを知っているとどんな悪いところに行くのか、と(笑)。仙台に伊達正宗像が立っているために伊達前といわれたところがあるのですが、その像が撤去されても、やはり伊達前と言われている。最近すごいなぁと思うのは女性のファッション誌の見出しですね。「この春のゆるふわコーデ」つまり今までになかったことばで、やわらかくてふわっとした服装をひとことで表現してしまう。「もてホワイト」は「今までにない清楚で人を引き付ける白」、というような長いことばをひとことで言ってしまう。そういった技術はいまだに生きていると言えると思います。
民謡や遊び唄
さらに、口承文芸の中で分かりやすいのは唄の分野ですね。リズムに沿って短い詩を繰りかえす、これが唄というものですが、いわゆる民謡と言われるものは、今では舞台の上で披露されるステージ民謡とか新民謡がイメージされやすいですが、もともとは仕事の唄、馬方の唄う馬子唄、材木を切って引き出す時に歌う木やり唄、大漁を祝う大漁節などでした。有名なのは田植え唄ですね。唄のリズムに沿って田植え作業を進めていく作業歌です。アメリカの黒人奴隷が鉄道敷設などで歌った唄が今のブルースの原型だと言われていますね。そのように自然発生的に生まれてくることばです。
もうひとつは遊び唄です。例えば盆踊りの唄、昔はリズムに沿って即興で歌詞を作って歌うことが多かった。そして唄の名人と言われる人は次から次へと唄を繰り出すことができたのです。その歌詞に、○○さんはいつも酔っぱらって失敗してる、とか入れて、くすぐりにしている即興の唄でもありました。また、子供たちがうたうわらべ歌。「ずいずいずっころばし」とか「かごめかごめ」など。これらやこどもを子守するときの子守唄なども民謡のひとつの分野です。
語り物-浪花節や瞽女唄から寄席芸まで
民謡に近いのが語り物といわれる分野です。今はなじみが少なくなりましたが、半世紀前くらいまでは娯楽として生活の中で非常に大きなウェイトを占めていたものです。語り物とはリズムや節を持った短い詩を紡いでいってひとつの長い物語を語ると口頭芸で、一番イメージしやすいのは浪曲・浪花節だと思います。二、三十年前の夕方にテレビで広沢虎造浪曲全集のコマーシャルをやっていたのを覚えています。主に戦の物語、あるいは義理人情の物語を情感たっぷりに唸る。リズムに乗せてひとつの物語を語る。泣ける話が多いのでお涙ちょうだいなどと揶揄されたりもしますが、村の中で半プロ的な人がかくし芸的に語ることもありました。
その後、語り物の芸を持って世の中を渡っていくプロの口頭芸、話芸の人たちが出ました。そういう人たちが定期的に村落共同体を回って芸を提供していた、その一例として門付けをする瞽女(ごぜ)さんの写真を出しておきましたが、この瞽女さんは目の見えない女の人達で、三味線を弾きながら瞽女唄、悲劇をモチーフにした唄、親と子の別れなど可哀想な唄を歌いました。聞き手は農山村の女の人たちで、それを聞きながら、かわいそうだと涙を流す、今の韓流ドラマの視聴者と同じ構造になっていますね。新潟県の長岡とか上越市の高田とかに瞽女さんの本拠地があったのですが、そこから数か月間巡業に出て、大体、なじみの家、大きな庄屋さんの家などに泊めてもらって、そこで瞽女唄の公演を開いて、お米などをもらって次の土地へ行く、という生活をしていました。瞽女さんは目が見えない、もしくは弱視の人たちですので、かつてはこういう口頭芸は障がい者のひとつの社会参加というか、社会福祉がきちんとできていなかった時代に、芸を持ってなんとか生きていく、セーフティーネットでもあったことがうかがえます。
このような口頭芸が舞台に入って行って、さらに職業として専業性を高めていくと、寄席に出てくるような落語や講談、漫才に繋がっていくのです。しかしそういう芸人さんの芸の根っこには、宗教性もまた存在していることも見逃せません。瞽女さんの三味線の糸が切れたのをもらうと、蚕がよく育つ、あるいは旅芸人に、着物に袖を通してもらうと子供が丈夫に育つ、旅をするということ自体が一種の宗教性を持った人たちなのだと思われていました。そうした宗教性を持ったひとだから、不思議な物語を語れるのだということですね。物語を語るということが、ひとつの宗教儀式だったといえます。物語を創ること自体が普通の人にはできない不思議な行為だったのです。そういう考え方があったということに注目しておきたいと思います。
昔話の特徴
民間説話を昔話・伝説・世間話という三つのジャンルに分けて考えようと言ったのは、さっき言ったように柳田國男ですが、なぜ三つにわけるかというと、それぞれが違った意味合い、機能を持って話されていたからです。どのように違うのかといいますと、まず昔話は、語り手と聞き手が、これは本当にはなかったお話なのだ、悪く言えばうその話なのだということをきちんと自覚したうえで話し、あるいは聞く、そういう説話だと言えます。いわゆるフィクション、この話は実在の場所や時間は関係ありませんということを自覚して聞く物語です。
「鈴木サツ昔話集」からの「人にもの食せたくねえ男の話」をお配りしましたが、鈴木サツさんは遠野の昔話を語る人で、このひとのお祖父さんかお祖母さんが遠野の佐々木ギゼに語ったそうで、この佐々木ギゼさんは柳田國男の「遠野物語」の題材の提供者です。なので、遠野物語の継承者と言えるひとたちです。
ほかの昔話と同じように、この「人にもの食(せたくねえ男の話」も「むかす、あったずもな。あるとこに」ということばで始まっている。このことばに注目していただきたいのですが、今の絵本でも「むかしむかし、あるところに」と始まっています。この「むかしむかし あるところに」が何を指しているかと言うと、「今ではない」時、「ここではない」ところ、で起こった話なのですよと宣言して始まるということです。時間や場所にしばられない空想の世界の話だということ、それが昔話の特質になります。
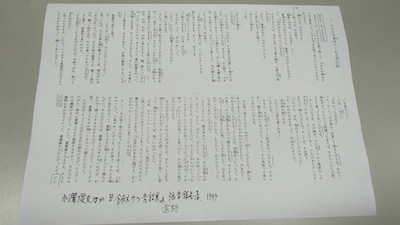
「人にもの食せたくねえ男の話」
※クリックすると拡大した画像が見られます(別ウィンドウが開きます)。
落語に「桃太郎」というのがあって、前座話ですが、こどもがむずかって寝ない、そこでとうちゃんが桃太郎の話をしてやるから早く寝ろ、と、「むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんがいました」と始めると、子供が「おとうさん、むかしむかしとおっしゃいますが、それはいつのことでしょうか?平安時代でしょうか、室町時代でしょうか」「そんなことはどうでもいい」「いえ、そうはまいりません、時代考証というものがございます」とくいさがる。「あるところ、とはどこでしょう?兵庫県でしょうか、岩手県でしょうか」さんざんそういうふうにつつかれて、おとうさんは「あぁ、うるさい、俺は寝る!」と寝ちゃう。すると「やれやれ、おとなとはたわいないものだなぁ」と下げになる。実はこういう聞き方は昔話の聞き方のマナー違反で、昔々の、ここではないところの、フィクションの話なんだと承知して聞くことがひとつのマナーになります。
昔話の大きな特徴のひとつは、語り口に形式がある、ということです。例に挙げた昔話でも、「むかす、あったずもな。」で始まり最後に「どんどはれ。」で終わっています。「昔々」ではじまり「めでたしめでたし」で終わる形式です。昔は各地域に根差した発端の句と結末の句があり、それらでくくられたものが昔話だと理解されていました。昔話とは、時間と空間に縛られないフィクションの話で、語り口に形式を持つ、ということをおさえておいてください。
伝説は事物と結びついて「歴史になりたがる話」
それでは、伝説や世間話は昔話とどう違うのか。伝説は英語のlegendに対応することばだと考えられています。歴史上の人物が成し遂げた偉業など、たとえばアーサー王伝説と呼ばれるものがありますね、また、「銀河英雄伝説」という宇宙戦争をテーマにした小説がありますが、叙事詩、英雄の一代記であるサーガを指して伝説と言ったり、また人が達成できないようなことをした場合、冬の無人島でサバイバルしたり、ですね、また個人の逸話や偉業、たとえば長嶋茂雄さんの虚実とりまぜた逸話や偉業を伝説と呼んだりします。
民俗学では伝説は、信じられているものであることを前提にします。そういうことが昔あったのだとされる、つまり歴史上の一時点でおこったこと、ノンフィクションですね。例えば、弁慶がここを通った時に、手形を残した岩だから「手形岩」である、など。弁慶が生きていた時代にここで起きたこととして話される。それが伝説の特徴です。そして事物と結びついていることが重要です。それがこれです!と指差すことができる。事物の由来として語られます。事物だけでなくことと結びつくこともあり、例えば坂上田村麻呂が大蛇を退治してくれた、喜んだ村人が村中に灯をともして田村麻呂を迎えた、それがこの火祭りの由来です、とか。昔鎮守様がこの村にやってきたときに、キュウリの蔓に躓いて落馬し、ゴマのとげで目を怪我した、それ以来この村ではキュウリとゴマは作らない、という作物禁忌の由来の伝説もあります。
新潟県と福島県の境にいる渡部さん、この人たちは昔は屋根に明り取りの破風を作らなかった一族でした。なぜかと言うと、この渡部さんは渡部綱という平安末期の武将のすえでして、渡部綱は源頼光の四天王と言われたひと、このひとが夜羅生門のあたりを通っていると、上から鬼の手が出て、兜をつかまれた。綱はあわてずに抜き打ちに鬼の腕を切り落とした。鬼が手を取り戻しに来るから七日間、厳重に物忌みをするよう安倍晴明に言われ、その通りにしていると、七日目に奈良から育ての親である叔母がやってくる。物忌み中なので会えないと言うと、育ててやったのに情けないと泣かれ、仕方なく家に入れると物忌みのわけを聞かれる。そこで鬼の腕を切り落とした顛末を話すと、そんな珍しいものはぜひ見てみたいということでしぶしぶ見せる、するとこれは俺のものだから返してもらうと鬼の本性をあらわして、腕を持って屋根の破風を破って逃げてしまった。それ以来渡部の家では破風をつくらないという伝承があります。
このように村や土地、一族の伝承を事物に結び付けて、ノンフィクションとして話すのが伝説です。そして話し方が自由だと言うのがひとつの特徴です。昔話のように一定の形式はありません。資料に、例として、東京都の日の出町の秀郷・将門伝説を出しておきました。藤太橋という橋にある案内板ですが、藤原藤太秀郷が戦いの陣を敷いたところです、と。このように、伝説は案内板や一冊の本という形でも伝承することができます。ことばにとどまらないということも伝説のひとつの特徴です。私たちの身の回りで一番多い民間説話はこの伝説です。観光地には一つや二つ、こういった伝説があります。事物が無くなってしまっても、実はそういうものがあったのですよ、という形で語り継がれます。それが伝説の面白いところです。地名やその由来という形でも話される。
柳田國男は伝説を「歴史になりたがる話」と評しました。その協同体なり、家や個人なりが持っている歴史観、民話研究家の松谷みよ子さんは「あったること」と言いましたが、私たちが考える過去の歴史、それはフォークロア、民俗的な歴史観なのでしょう。その協同体、家、個人を成立させている核となるもの、それが伝説です。先祖は平家の落ち武者ですという落人伝説の村は全国で400くらいあるそうで、ひとりで落ちて行ったはずはないので、最低7人ずつだとすると、源氏と平家のパワーバランスが逆転しかねない人数になります。民俗学者が考えているのは、そういう辺鄙な村に住むのは木地師と呼ばれるお椀の白木の器を作る人たちが多く、それらの人たちの由緒が分からなくなったときに、辺鄙な場所に住まざるを得ない理由があったはずだと考え、木地師は天皇家と同じ十六菊家紋を使うところから、実は私たちは高貴なものの末だ、とした。先祖に対するあこがれの気持ちから自分たちの歴史を作り上げていったのです。最後に、山奥の一番古い墓を平重盛の墓にして伝承するなど、ですね。そういう民俗的歴史が伝説というものです。
世間話は「世間に通用している噂話」
最後に世間話ですが、柳田國男は、「世間に通用している噂話」という意味でこのことばを提唱しました。世間一般で本当にあったと言われる話、ノンフィクションですが、それでは伝説とどこが違うかというと、その出来事が起きた場所や時間が話し手と聴き手に近しい時間と場所、身近な場所や時間で起きたとされる変わった出来事。奇事異聞が中心で、イメージしやすいのは、キツネに化かされた話とか、お化けが出た話。こういう世間話が今でも生産されている例として、資料に「ちびまる子ちゃん」の、父ヒロシがキツネに化かされたという漫画を挙げておきました。身近な時間と場所と言いましたが、聴き手が自分と連続性を持って感じられれば世間話として機能します。
都市伝説としての世間話
行ったことが無い場所でも、例えば、青山墓地に幽霊が出て、それがタクシーに乗る、なんて話がありますが、青山墓地に何らかのイメージを沸かせることができれば、話し手と聴き手に近しい場所だと言えます。青山墓地の幽霊の話などは、現在都市伝説などと言われて商業メディアを賑わせています。雑誌やテレビで興味本位に取り上げられているこの都市伝説は、民俗学から見ると世間話の現代版、都市生活を背景にした世間話の一ジャンルということになります。
1980年代に流行った、ハンバーガーには猫の肉が使われていて、目撃した人が口封じに2万円もらったなんて話がありますが、こういった話は繰り返し現れています。國學院大學は渋谷にありますが、教授から聞いた話です-少し前に渋谷の繁華街に渋谷食堂という店があって早い・安い・量が多いので有名でしたが、肉うどんは猫の肉を使っているから食べちゃいけない、という噂があったそうです。あるパターンの話を繰り返し聞かされるということですね。30年周期で同じパターンの噂を3回聞いたと先生がおっしゃっていました。
世間話は、今ここに居る私たちの関心に合わせて、興味や不安を反映して、ひとつのパターンにすべりこんで出来た話です。この、安くてうまいものは、実は変なものじゃないか、という話は、1000年前に書かれた今昔物語の中に、魚の干物を安く売る女がいて、うまいうまいと食っていたらそれはヘビの干物だったという話があります。芥川龍之介が「羅生門」の中で流用していますが。このようにある種の発想のパターン、これを話型といいますが、に乗って噴出してくる、その話型のうち特に現代のファーストフードやパソコン、携帯電話とか車とか、現代にしかないものを背景としているものを特別に都市伝説と呼んだりしているわけですね。
伝説と世間話の違いで、もうひとつ触れておかなくてはならないことは、世間話は長く伝えていくということではなく、現在の生活に結びついて一過性でパーッと流行って、すたれていく噂話ということです。
ハナシとカタリ
昔話は語りに形式がある。伝説や世間話は形式にこだわらず自由な発話で話すことができる。そこで、昔話はカタリ、伝説や世間話はハナシだとまとめることができます。カタリとは古事記や日本書紀にも出てくる古いことばなのですが、ハナシという日本語は室町時代にやっと出現する新しい技法です。「話」を古くは「カタリ」とも読ませていました。ハナシということばが現れた時は「咄」や、今落語などに使っている「噺」という国字を充てていました。ハナシはお伽衆やお話衆と呼ばれる人の出現とともに現れてきたことばです。この人たちは大名などのそばにいて、眠気覚ましに、もしくは教養としてさまざまなことをお話しするのが役目でした。軍談や和歌・茶の湯の教養などについてエピソードを通じて大名に伝える、友達兼家庭教師といった役割で、結構地位のある人が多いのです。世情のことも敏感に察知して、格式張らずに伝える、そういう新しい話法がハナシとして定着していったのだろうと言えます。
カタリとしての昔話:発端句と結末句
カタリはその反対に、特別なときに格式張って、何らかの重要な意図をもって伝える談話の技法で、昔話の中にその痕跡を残していると考えることができます。昔話は発端の句、結末の句を持ち、独特の語り口とリズムを持ちます。例に出した「人にもの食せたくねえ男の話」では「むかす、あったずもな」という発端句、「どんどはれ」という結末句がありますが、これらは今でも遠野の物語の代表的な発端句、結末句ですが、全角各地にさまざまな言い方があります。秋田県のカタリ納めの句は「とっぴんぱらりのぷう」で、高知県では「とんとむかし」などと始まり、「むかしまっこう」「むかしまっこう猿まっこう」などと終わります。「日本昔話大成」(角川書店1980)
この初めの句と終わりの句の効用は何かと言うと、「むかす、あったずもな」と言われると、語り手も聴き手もこれから昔話の世界に入るのだ、フィクションの話だから信じたり詮索したりしたらいけない、娯楽の話なのだ、と宣言する、それが発端句の役割です。
今のストーリーテリング、図書館などでのお話の会でも、今からお話の世界に入りますよ、とセレモニー的なことをする、例えばローソクを灯すとか、扉を閉めるとか、映画の始まりのブザーのように、それは合図として機能しています。結末句は、昔話の世界はここでお終い、ここからさきは日常ですよ、カタリからハナシの世界へ戻りますよ、ということを宣言するのです。
結末句は「めでたしめでたし」で代表されますが、話しはこれで終わって、いいことばかりになりました、というものが多くあります。例えば「どんどはれ」というのは「すべて はれ」ということですね。「はれ」は果てると同時に晴れる、またお開きになりました、との宣言、新潟では「これで いちご さけた」というような言い方をしますが、いちごは一期一会の一期ですね、さけたは栄えた、つまり登場人物はそれから一生栄えた、ということですね。高知の「むかし まっこう」は「昔はこうでした」と終わりを宣言している。
昔話の終わりは聞いていればわかるものなので、結末句には遊び心が増していって、例えば「むかし まっこう」に「猿まっこう」というまったく関係のないことばを付けます。「むかしまっこう 猿まっこう 猿のつびゃぁ赤い」などと子供のよろこびそうなことばをどんどん付けていっています。最後は早口言葉につなげていくものもあります。このように昔話の語り納めは遊び心にあふれているのです。新潟の「一期 栄えた」も一期が分からなくなって、市になって、「市が栄えて めでたい」となったり、「苺が栄えて めでたい」とか。
昔話のカタリのリズム
昔話は一定のリズムに乗って語られ、聴き手もあいづちをうつようになっています。このリズムに乗ることで理解が深まり、興に乗ることができるのです。このリズムが形作られるのは、ひとつには特定の語尾です。この場合の「むかす、あったずもな」の「~したずもな」ですね。古文の助動詞の内、伝聞・推定の助動詞です。「~だったそうですよ」ということです。京都や鳥取のほうでも伝聞の助動詞「げな」を使います。「げなげな話は嘘だろう」などとも言います。このように、昔話は、本当かどうかわかりません、私の聞いた話です、ということを常に宣言しながら進んでいきます。
また、地の文に短い会話をいれて、ことばのやりとりで成り立っているように作られています。さらに、唄のパートも意識的に入れてリズムを作ります。例えば有名な「おむすびころりん」では「おむすびころりん すっとんとん」などとネズミに歌わせたりします。「舌切り雀」では「かわいい雀はどこ行った」とおじいさんが唄を歌いながら雀を探したりします。また、ぐらぐらぐら、とか、わらわら わらわらとか、ぱらん、ぱらん、ぱらん、などとさまざまなオノマトペを入れてリズムを作っていく。このように一様のリズムではなく、いくつものリズムを重ねて盛り上げていく。根っこには一定の語尾を使って話していく、土地のことばのリズムがあります。
現在、観光の昔話の語りがたくさん行われていますが、そこでは失われてしまったリズムもあります。それは相槌のリズムです。かつての囲炉裏端で語られた昔話の場合は、子供たちが発するべき合いの手としての相槌がありました。福島県では「さーさ」などのことばが聴き手の発するべきことばとしてありました。例に挙げた遠野の昔話では「あるとこに、なにもかも欲ァ深くて、人さもの食せたくねぇ男があったったずもな(おーど)」と合いの手を入れます。語り手の息継ぎのところに、聴き手が「おーど」と入れるのです。かつての昔話は語り手がひとりで語るのではなくて、聴き手とともにカタリを作り上げていく。聴き手の様子をみてゆっくりと語ることができる、また、「おーど」の声がだんだん小さくなっていくと、語りも小さくなって、寝かしつけることができる、などのメリットがあります。あるいは、聴き手が何度も聞いたことがある、別の話がいい、という場合は聞いたことがあるという、すると語り手はリズムがとりづらくてカタリがうまくいかないというふうに、カタリを阻害したり、聞きたい話をリクエストすることもできます。このようにかつてのカタリは語り手と聴き手の共同作業だったと言えます。
昔話はいつするのか
発端の句、結末の句、相槌、リズムなどはカタリの中にある形式ですが、カタリの外にも形式があります。野村純一著作集によれば、「昼むかしの禁忌」と言って、昼に昔話をすると、ネズミに小便をかける、とか、鬼が笑うとか、裏山の寺の鐘が崩れるなど、不吉なことがおこると日本各地で言われています。昔話は夜にするものだという規範意識がかつては存在していたのです。また全国で言われるのが「節季ナンズの正月ムカシ」や「話は庚申様」などで、御節句とか庚申講、お正月などの特別な晩に昔話を語るべきで、普段は長々と昔話などしてはいけないという意識が存在していたのだろうと言われています。
昔話はかつての村落共同体において、ある特定の日の夜に語り手も聴き手も形式を守って行われるべきものであって、普段の日にはみだりにするものではない。昔話には一定の記念性、宗教性があって、それが子供の娯楽になっていったと柳田國男や民俗学者は考えています。例に挙げた「人にもの食せたくねえ男の話」では、妖怪に追われた男が最後に菖蒲とヨモギの間に入って隠れたのですが、その妖怪は菖蒲とヨモギのにおいをかぐと腐ってしまうものだったので男は助かる、その日はちょうど五月の五日の節句の日だったので、節句に菖蒲とヨモギを屋根に挿したり、菖蒲湯に入るのは、魔よけなんだと、五月五日の菖蒲とヨモギの由来になっています。このように、なにか行事と関連付けて話される、そういう昔話がいくつかありますが、これは五月五日の夜に語られるべき特別の話だったのではないかと考えられています。
語り手たち
そして昔話を語ることができる人たちは特別な人、と見られていたふしがあります。新潟や東北では、昔カタリの上手な人たちをカタリジサ、カタリバサなどと呼んでいます。カタリジサ、カタリバサは、カタリがうまいことと同時に、集落で一定の地位を認められている。カタリがうまいから子どもたちをまかせても大丈夫だ、と村落共同体でカタリの特技を持った人と認められていた。それはその人たちが、かつては村落の儀式や信仰の上でなんらかの役割を持っていた痕跡ではないかと民俗学者の中で考える人もいます。
今観光の昔話では語り部などと言われますが、この語り部ということばは万葉集などにある古いことばのリバイバルです。民俗学ではカタリの名人たちをカタリジサ、カタリバサと呼んでいます。この人たちがどうやってカタリを作っていくかを見ていきます。
昔話の伝承
賀島飛佐さんという人は岡山県で昔話の語り手として知られていた方です。三百話くらいの話を語ることができた。カタリは唄のように、語り出すと次の句がすっと出てくるので、百話以上を管理している人は日本に何人もいました。賀島さんが三百もの話をどこから仕入れているかと言うと、それが話の伝承経路です。両親、母方の祖父母、父方の祖父母、舅姑、から昔話を聴き、それ以外の伝承者、親類や寺の和尚さんや法印さん、裁縫やお茶の先生、臼や籠の職人、木挽きや炭焼き、鍛冶職人、茶碗売りやその他の来訪者、湯治客や奉公先の老婦人などなど、からも話を聴いた。元来昔話が好きだった飛佐さんはそれらを心に留め、老境にさしかかってから孫世代にむかって、すらすらと流れるように再生していったのです。そこにいい聴き手がいることによって、次々と思いだしていく。
語り手は研鑽を積んでなる、というよりも、自分の中に幼児期から貯めていたものが熟成されて、いい熟成度になったときに堰を切ったように外に流れ出すものです。飛佐さんが話を聴いた人たちは、血縁関係の年長の人、近所の人、村へやってきた訪問者の三つに分けられます。家系伝承、村落伝承、来訪者伝承です。このうち、世代を超えて伝えられる伝承に対して、来訪者伝承は同時代に撒き散らされていく伝播という意味合いもあります。
伝承の場としての囲炉裏-共同作業の場
野村純一著作集から、山形県の優れた語り手である土田さんの家の囲炉裏をひいてみますと、伝統的な囲炉裏で一番いいところは後ろに大黒柱や神棚を背負ったヨコザ(カミザ)、ここには主人が座ることになっています。「ヨコザに座るは猫・バカ・和尚」というように、主人より偉い和尚さんか、場をわきまえない猫かバカ、というわけです。また、ヨコザに座るなら米一升買う、酒一升買う、というようにルールがあるところもあります。
ヨコザから見て右側がカカザで、後ろに台所を控え、主婦が座る場所です。一家の主婦権を象徴するところなので、勝手に座ってはいけない。
ヨコザから見て左がキャクザでお客さんが座るところ。そして嫁とか子ども、客でも出入りの職人や行商人などはヨコザの正面のキジリ(シモザ)に座ります。後ろには薪が積んであり、この座から突っ込んで燃す。一番煙が来るところなのです。
このように座る場所がきっちりと決まっている囲炉裏の、ヨコザに座る主人からは家に伝わる伝説や一家の由来が子どもたちに伝わっていく。また、カカザに座る主婦からは嫁いできたお嫁さんや子供たちに、家の昔話が伝わっていく。そして、家に来たお客様や出入りの商人から世間話がキジリの子ども達に伝えられる。子ども達はそれをじっくりと聴き、大人になってヨコザやカカザに座るようになったら、それをまた子どもに伝えていく。昔話や伝説はこのように囲炉裏端で伝えられていたのです。実際にはそのほかに山仕事の最中に、とか、子ども同志遊んでいる中で、とさまざまに伝えられたのでしょうが、囲炉裏は特に印象的な空間であり、ことばが交差する場であり、その場でことばを蓄えた子ども達が昔話の語り手、伝説の担い手、世間話の広め手になっていくのです。ことばを仲立ちにして個人と社会がつながっていく共同作業の場だと言えます。

ことばの文化は聴き手と話し手があってこそ
また、語り手が口をそろえて言うことですが、これまで語る機会がなかった。なぜなら誰も聴いてくれなかったからだ、と。テレビやゲームに夢中で聴いてくれなかった。ですから、今、我々の伝統的なカタリの文化が廃れているとすれば、それは語り手が少なくなったからではなく、聴き手が減ってしまったこと、語り手と聴き手が出会わなくなったので、語り手が発話できなくなったということなのです。
ことばの文化はことばを話す人がひとりですることではなく、聴き手があってはじめてことばになり、語り手が語り手として目覚めるのです。それが、昔話の伝承の現在から言えることだと思います。
以上
(文責:事務局)
|

![]()
![]()